外部寄生虫(ノミ・マダニなど)
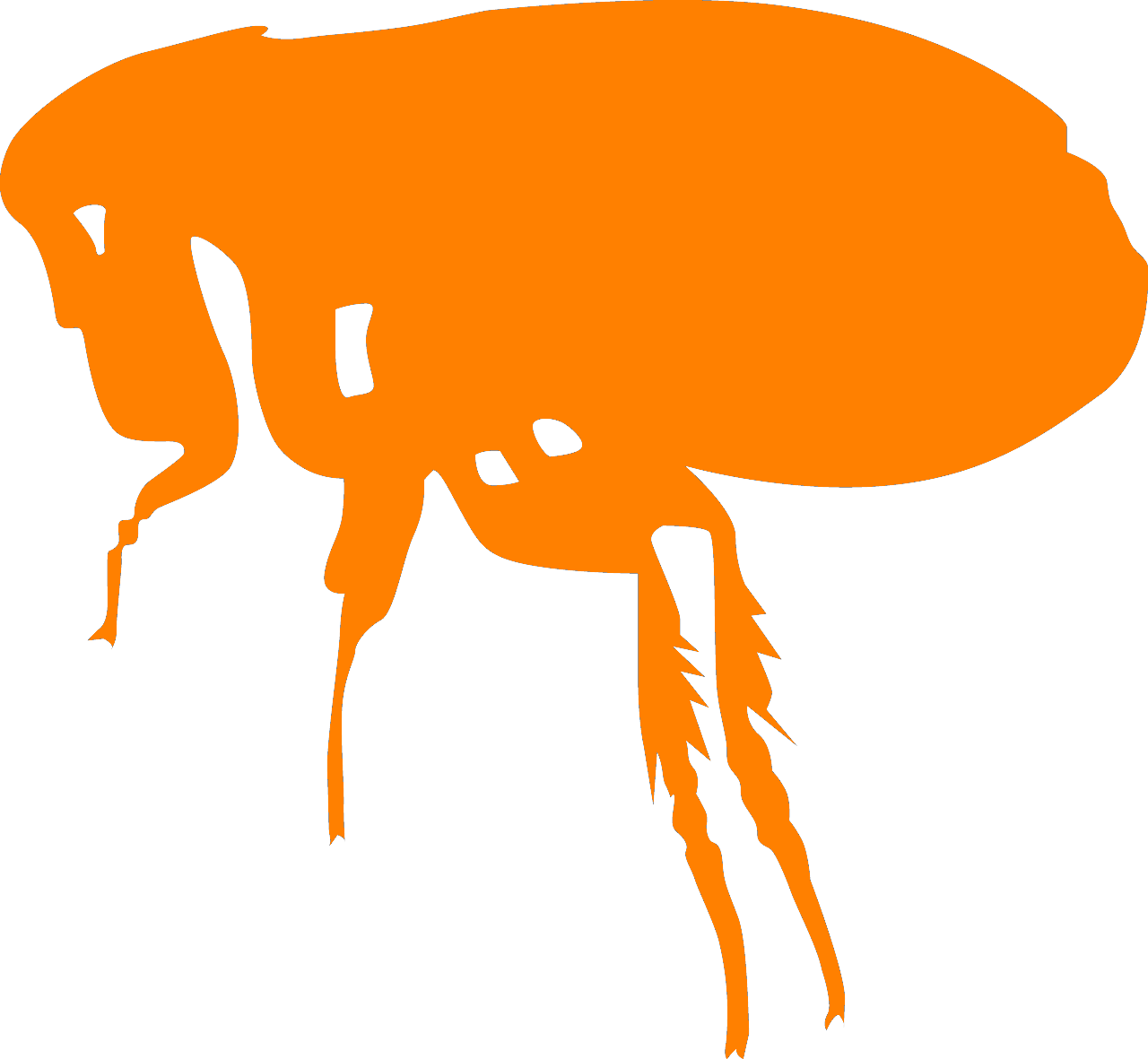 ノミ
ノミ
ノミはワンちゃん・ネコちゃんの体表に寄生するもっとも一般的な寄生虫です。
卵、幼虫、さなぎ、成虫と成長し、成虫が動物に対し寄生能力を持ちます。
大きさ:成虫で約2㎜。
発見できるノミは成虫で、寄生数の約5%だといわれています。
以下のことが当てはまる場合は予防・治療が必要な場合があります。お気軽にご相談ください。
特にノミは気温が13度を超えると活発に活動し始めます。温暖な室内は1年中ノミにとって最適な環境のため、一旦屋内に侵入してしまうと大変。定期的な予防・駆除が必要になってきます。( ..)φ
マダニはクモの仲間で、卵、幼ダニ、若ダニ、成ダニと成長し、幼ダニのうちから寄生能力を持っています。大きさ:ゴマ粒大(幼ダニ)~30㎜(成ダニ・吸血後)やぶや草むらなどに生息しており、草の先などで動物に寄生する機会を狙っています。 巷で話題のの媒介も示唆されています。 温かくなると、虫たちの活動は活発化します。
卵、幼虫、さなぎ、成虫と成長し、成虫が動物に対し寄生能力を持ちます。
大きさ:成虫で約2㎜。
発見できるノミは成虫で、寄生数の約5%だといわれています。
- ノミの生活環
- 動物に寄生したノミの成虫は体表で吸血と産卵を繰り返します(寄生後24~48時間で産卵開始)。
- 卵は動物の体から落下し、そこで幼虫になります(屋内の場合、お部屋のカーペットや畳、動物の寝床などでふ化します)Σ( ̄ロ ̄lll)。
- 幼虫はノミの成虫の糞などを食べ、脱皮を繰り返し成長してゆきます。
- 成長した幼虫は繭を作ってさなぎになります。
- さなぎから成虫になったノミが再び動物に寄生します。
- ノミの症状(被害)
ノミに寄生された動物は刺されることにより、かゆみ等の症状が現れます。また、ノミが媒介する病気もあります。- 貧血
ノミは動物の血液で生きているので、吸血を行います。
1匹1匹が数量は少なくても、大量の寄生を受けると貧血を起こす危険があります。
特に体力の弱い子犬・子猫・老齢動物はその危険性が高まります。 - 2次感染
ノミに刺された個所を犬や猫が自虐(噛んだり、ひっかいたり、なめたりすること)することによりできた傷より細菌が感染し、化膿してしまうことがあります。 - ノミアレルギー性皮膚炎
ノミに繰り返し吸血されることにより、アレルギーを起こし、激しかゆみと皮膚炎が起こります。
一旦アレルギーの症状が出てしまいますと、少数の寄生でも激しかゆみが起こります。 - 瓜実条虫
ノミの体内で発育し、犬や猫がノミをグルーミングなどにより食べてしまうことにより感染します。
寄生部位は小腸で、下痢や嘔吐の原因になります。
瓜実条虫の片節(体の一部、米粒大の大きさ)が糞便や肛門周囲に付着することにより、動物が肛門をこすり付けるような行動が見られることもあります。 - 猫ヘモプラズマ(ヘモバルトネラ)症
猫の赤血球表面に寄生する マイコプラズマの一種。
貧血、発熱、元気消失などの症状が見られ、感染は感染動物による咬傷、ノミ・まだにによる媒介で成立します。 - 猫ひっかき病
猫には症状が出ませんが、感染ネコに人間が引っかかれたり、噛まれたりすると、リンパ節が腫れて発熱や頭痛などを起こすことがあります。 - ノミによる人へ被害
ノミは動物だけでなく、人も吸血します。その祭、発赤やかゆみ等が見られることがあります。
- 貧血
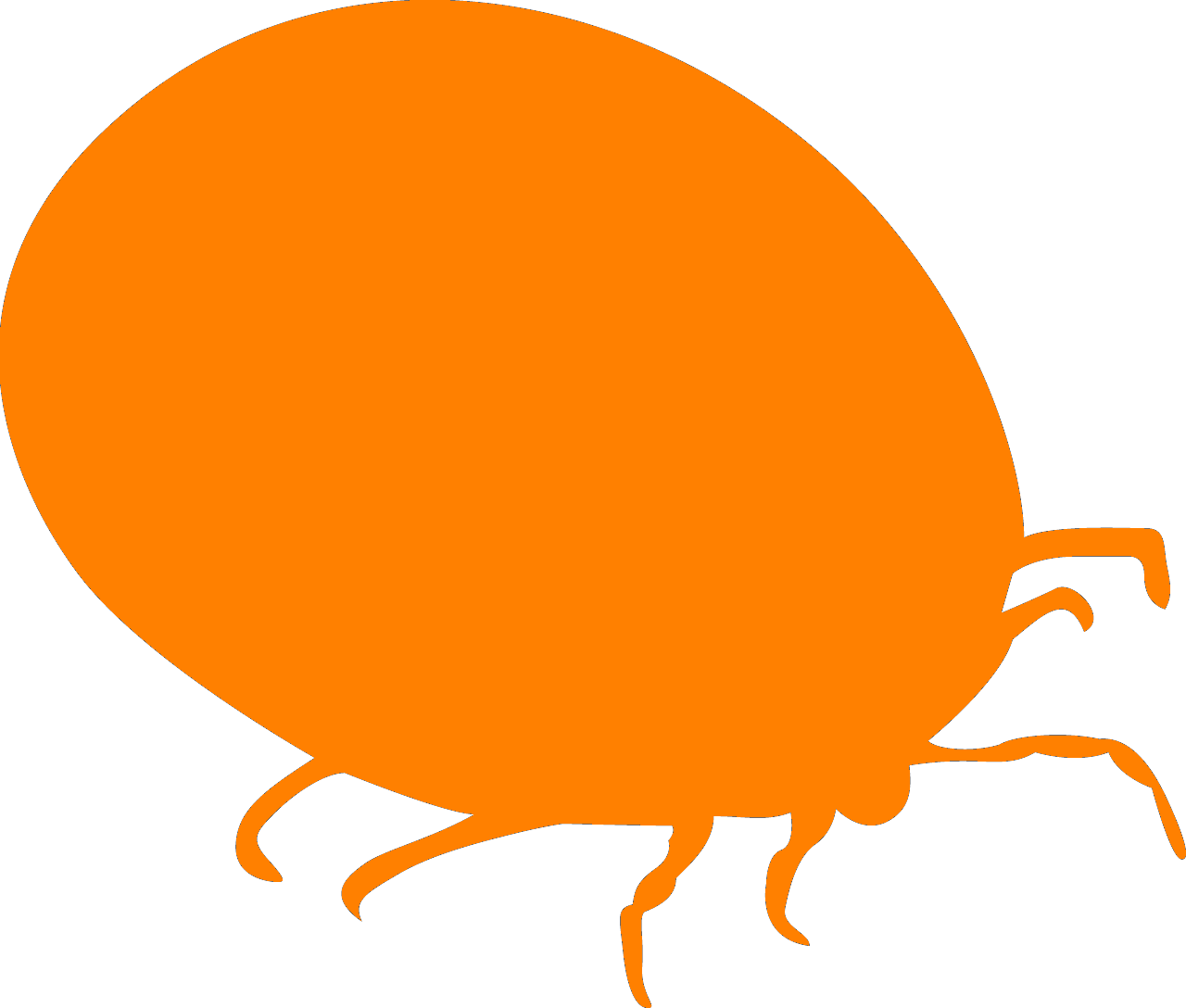 マダニ
マダニ
- マダニの生活環
- 卵から孵化した幼ダニは吸血源になる動物に寄生する。
- 吸血後、寄生した動物から脱落して地上で脱皮する(幼ダニ→若ダニ)
- 地上に落ちた若ダニは再び寄生する動物を見つけ、寄生・吸血する。
- 飽血(満腹)になると再び地上に落下し、脱皮する(若ダニ→成ダニ)
- 成ダニへと成長すると、3回目の寄生・吸血を行い、雌ダニは産卵を行う(1か月で最大3000個の卵を産卵…)。
- マダニの症状(被害)
- 貧血
マダニの唯一の栄養源は血液なので、寄生数が多数になると貧血が起こります。
1匹1匹の吸血量は少なくても、多量の寄生により貧血が起こる場合があります。 - 2次感染
ダニが動物に寄生すると、皮膚を突き刺して吸血を始めます。その際、振り落とされないようセメント状の物質で動物の体に口を固定します。無理やりマダニを取ろうとすると、口の部分が残ってしまい、化膿などの原因となります。 - 犬バベシア症
バベシアという原虫がマダニによって媒介され、赤血球に寄生することにより、赤血球が壊され、貧血、発熱、食欲不振、黄疸などが見られ、死に至る病気です。
治療を行って、貧血などの症状が治まっても、バベシア原虫が体内から完全に消失することはありません(体調不良など免疫の低下をきっかけに再発することがあります)。
その他にマダニはライム病、Q熱、日本紅斑熱などを媒介することもあります。 - 貧血
以下のことが当てはまる場合は予防・治療が必要な場合があります。お気軽にご相談ください。
- 外で遊ぶことが多い or 外出をよくする。
- 皮膚をかゆがる(体を掻いたり、噛んだりしている、湿疹が出来ている)。
- 首筋や体に黒い粉がのようなものがついている。
- お散歩友達、ご近所さんにノミ・マダニの被害にあった方がいた。
- お散歩道で野良猫をよく見る。
- お庭に野良猫が遊びに来る。
- ノミを見た。
- マダニを見つけた(鼻の周り、目の周り、耳の後ろなどによく寄生しています。イボと間違えることもあります。)。
特にノミは気温が13度を超えると活発に活動し始めます。温暖な室内は1年中ノミにとって最適な環境のため、一旦屋内に侵入してしまうと大変。定期的な予防・駆除が必要になってきます。( ..)φ
